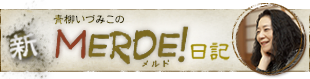かつて文士たちが集った家。
今は、グランドピアノの音色が響いています。
ピアノはずっとやめるタイミングを計ってたのに、やめそびれちゃった。私はピアニストとしては手が小さくて指が短いから、マッチする曲は限られているし、いわゆる万人受けするタイプじゃないっていう自覚もあったんだけど(笑)。一方、文章を書くのはピアノに比べるとラクで楽しい。スルスル書けちゃう。最初のうちは、ピアニストが文章を書くなんてけしからん、という批判も受けましたが、いつの頃からか、だいたい年に一枚CDを出して、一冊本を出す。これが自分にいちばんしっくりくる活動スタイルになっていきましたね。
青柳いづみこさんは、ピアニストとして活動しながらエッセイや評伝を執筆し、どちらの分野でも高い評価を受けている〝二刀流〟。二台のグランドピアノが鎮座する広い居室は、ピアノの譜面以外にも、さまざまなジャンルの本や資料でいっぱいだ。
ここは、私がフランスに留学したタイミングで、父が実家の一階をピアノ室に改装してくれた部屋なんです。一台はハンブルクの工場から運んだスタンウェイのB型で、夫が結婚指輪の代わりに贈ってくれたもの。もう一台は銀座で買ったヤマハのC7。もちろんどちらも現役で、用途によって使い分けています。
そう語る青柳さんの実家にして現在の住まいがあるのは、かつて「阿佐ヶ谷文士村」と呼ばれた東京都杉並区阿佐ヶ谷だ。井伏鱒二や太宰治などの文筆家たちが多く住んだ地域で、彼らは「阿佐ヶ谷会」という会合を開いては盛んに交流をしていたという。まさに、その会場が、青柳さんの祖父の家だった。
祖父の蔵書を読み漁った少女時代。
やがて、ピアノでフランス・マルセイユへ
私の祖父は、フランス文学者の青柳瑞穂です。当時の典型的な文士で、一生活者としての能力はまるでなかったみたい。裕福だった祖母の実家をあてにして、ろくに働きもせず、自分の本や趣味の骨董品収集にどんどんお金を使ってしまうような人だった。それを苦にして、祖母は早くに亡くなっています。だから父は、祖父のことをずっと許していませんでしたね。
父が選んだのは化学の道。親とは真逆の方向へ進みたかったんでしょう、東京工業大学の電気化学の教授でした。そして母は、父よりも十一歳年上で、最初の夫を事故で亡くし、二度目の結婚でした。親戚のつてを頼って、故郷の兵庫県から東京に働きに出て、父と知り合ったとか。
一九五〇年、私が生まれたのは、世田谷区駒沢の家でした。詳しくは覚えていませんが、一つ家に、何家族もがギュウギュウと身を寄せ合って暮らしていたそうです。終戦まもない時期ですから、仕方なかったんでしょうね。それから私が三歳半のとき、家族三人で祖父のいた阿佐ヶ谷に移り住みます。祖父の家──三つの和室と茶室が一つある木造平屋に接する形で、二階建ての家を父が建てたんです。一階にキッチン、リビング、トイレ、風呂、二階に父母の寝室と私の部屋がある、一般的な造りの家でした。
祖父の家と行き来できる通路は一応あったものの、交流は全くありませんでした。当時まだ月一回の阿佐ヶ谷会は続いていて、隣にはよく文士たちが来ていたんですが、それで、夜、酔って騒ぐ声が聞こえてくると、父はとても不機嫌になりましたね。心底、文士たちの生きざまが嫌だったんだと思います(苦笑)。
しかし、青柳さんだけは時々、祖父の家に上がり込むことがあった。お目当ては祖父の蔵書。阿佐ヶ谷会の会場に使われていた六畳間と八畳間を通り過ぎ、奥にある祖父の書斎へ。
戦後の日本では翻訳ブームが起き、フランス語が堪能な祖父のもとにも多くの仕事が舞い込んだようです。おかげで、その資料を含め、祖父の蔵書はたいへんな量でした。それに、全集のうちわずか一作の翻訳を担当しただけでも、出版社は全巻を送ってよこすので──。子どもの頃から本好きだった私は、祖父の書斎にいっては本を調達し、ギリシャ神話からドストエフスキー、ジョイスまで、さまざまな本を読み漁っていたんです。
時には、祖父の晩酌に付き合うことも。カラスミやこのわたなどの珍味はその時に覚えたかな(笑)。茶室の押し入れにしまってあった骨董のコレクションを見せてくれたこともありました。ただ、別段、私が祖父に懐いていたとか、可愛がられていたという記憶はありません。祖父は色白のハンサムで、晩年までとにかく女性にモテる人でしたけど、孫娘の扱いには、いつもどこか戸惑っている感じでした。
音楽との出会いは四歳。父母が所属していた東京女子大クワイア(合唱団)の付属教室に通い始めたのだ。
そこで受けた音感教育が、音楽家としての下地になったことは間違いないと思います。やがて、すぐ近くに住んでいた叔母の家にあるアップライトピアノを弾き始めて……。五歳になると、自分用のピアノが家にやってきました。母の実家の山の木を売ったお金で買ってくれたものです。六歳からは桐朋学園による子供のための音楽教室に通い始めて、本格的なピアノ修業が始まりました。ただ、その時、ピアノを置いていたのは通りに面したところにあるリビングダイニングで、近所からも音について苦情がきたので、奥の三畳間に押し込みました。
初めてグランドピアノを迎えたのは、小学校五年生の時。アップライトピアノを下取りに出して中古のグランドピアノを買ってもらいました。置き場所は、やっぱり奥の三畳間。すごく狭かったですね。
文章修業の方はというと、中学二年生の時に童話を創作。気の合う友人と、二人だけの同人誌を作った。
同人誌といっても、印刷したものではなく、交換日記みたいなものでしたけど、すごく楽しかった! その友人は、音楽以外の文学や美術、演劇など文化的なことを話せる貴重な相手でした。彼女との会話は、常に心のチャージでした。というのも、高校は東京藝術大学付属音楽高校ピアノ科に進んだのですが、周りは皆、当然のように音楽に邁進してきた人たちばかり。話題の偏りというか、物足りなさは、どうしても感じてしまって……。もちろん、ピアノをうまく弾くためにはたくさん練習しなければならないのですが、それが主になるのには違和感がありました。
ところで、その高校には、全国から生徒が集まっていたので、クラスメイトのほとんどが下宿暮らし。実家から通っていた私は羨ましくて……。そこで、東京藝術大学一年の後半からは、私もピアノ付きの下宿へ引っ越すことに。留学する先輩が使っていた部屋を譲ってもらうかたちでした。中野新橋にあった通称「ピアノ・アパート」。住人は上から下まで、皆、ピアノを弾く人たちばかり。と言っても防音壁ではないので、隣人が今、何の曲を練習しているのかはダダ漏れなんですが、大きな交差点脇という立地で、近隣住民からの苦情を気にしなくていいのは気楽でしたね。広さは六畳+キッチン。みんな、ピアノの下に布団を敷いて寝ていました。お風呂はなかったので、誘い合わせて銭湯に行くこともありました。
三年になると、父の友人が、娘さんの将来に備えてしつらえたキッチン付きの防音スタジオを使わせてくれることになって、そちらに移りました。ここは、十畳の広さがあったので、快適でしたね。
そして七五年、東京藝術大学大学院修士課程を修了した青柳さんは、フランスへと旅立っていく。国立マルセイユ音楽院に留学することにしたのだ。
そこを選んだのは、祖父の影響で子どもの頃からフランス文化は身近なものだったから。また、それまで師事していた安川加壽子先生もフランスで教育を受けた方だった。そしてマルセイユ音楽院は、私の子供の頃の演奏を聴いて「ブラボー」と言ってくれたピエール・バルビゼ先生が院長をなさっていたから。
フランスで住んだのは、マルセイユにあるアパルトマンです。中央に食堂、あとは三つの部屋があって、アルメニア人の大家と私、あとは空き部屋だったかな。そこにアップライトのピアノをレンタルして置いていました。懐かしいのは、キッチンにあった大きなオーブン! 南フランスの食材はどれも素晴らしくて、何をどう作っても、ちゃんとおいしくなる。よく作ったのは、羊のロースト、ブイヤベース、ポトフ、ラタトゥイユ。昔から料理は割と好きな方でしたけど、フランスでの料理は特に印象的でしたね。
音楽院は一年で卒業となるので、そのあとは他学科の生徒のためのコレペティトゥア(伴奏者)として働きました。料理はおいしいし、生徒たちはかわいいし、仕事もあるし。このままもう少しフランスにいようかとも思ったのですが、そんな矢先、不思議な夢を見るように……。マルセイユの隣の駅が阿佐ヶ谷だという夢(笑)。これは帰れということだなと思って帰国することにしました。すっかり日本語が下手になっていたことも気がかりでしたし、学生時代に出会った夫とも、長いこと遠距離恋愛状態でしたからね。
〝ものを書くピアニスト〟としてまた、ドビュッシー研究家として
帰国した青柳さんは、八〇年、東京・イイノホールで初リサイタルを開催。その内容は毎日新聞紙上で高く評価され、ピアニストとして順調なスタートを切った……かに思えた。
もちろん、最初は順調でした。でも、徐々に何か納得がいかなくなっていったんです。ピアニストとして売れようと思ったら、自分が弾きたい曲ではなく、お客さんが喜ぶ曲でコンサートを構成しなくてはいけない。でも、それは自分のやりたいことではない気がして。小さすぎる手の問題にも悩まされました。そんな中、ムクムクと沸き起こってきたのが、文章を書くことへの思いだったんです。それで八三年、東京藝術大学大学院博士課程に入り直すことに。やりたかったのは、ドビュッシーの研究論文の執筆です。
ところが、そう決めた途端に妊娠して、いきなり休学に(苦笑)。でも、娘が二歳になった年、奨学金をいただいて今度はパリに行って研究に打ち込みました。七カ月間、ほぼ毎日フランス国立図書館に通って資料を読み込んで。その時、滞在したのは、キッチン付きの屋根裏部屋で、名前だけは立派な「芸術ホテル」という安宿でした。
ちなみに、結婚してから夫婦で住んでいたのは茨城県つくば市にある庭付きの一軒家。広くて快適だったけど、ピアノはずっと阿佐ヶ谷の実家に置いたままだったので、夫が山口県に転勤になった頃から、私と娘は阿佐ヶ谷で両親と暮らすように。それからも夫は単身赴任続きでしたけど、数年前に定年を迎えてからは、阿佐ヶ谷会の会場だった八畳間を居室としています。祖父が亡くなってからは、改築して二つの家の行き来をしやすくして使っていましたから。
八九年、研究の成果を綴った論文「ドビュッシーと世紀末の美学」で博士号を取得。さらに翌年、エッセイ集『ハカセ記念日のコンサート』で念願の文筆家デビュー。青柳さんは、自身の目指す姿に一歩ずつ、近づいていく。
CDデビューが少し遅くて九六年。八九年から始めた企画公演「ドビュッシー・シリーズ」を音源化した『ドビュッシー・リサイタル』が最初でした。当時は、ドビュッシーだけでコンサートをやるなんて、本当に画期的だったので話題になりましたし、ファンもついた。それが最近ではドビュッシーもすっかりメジャーな作曲家に。先駆者としては、嬉しいですね。
そんなキャリアの中、忘れられない出来事があるという。九七年、博士論文を一般向けの書籍として書き直し、『ドビュッシー 想念のエクトプラズム』として出版。その記念コンサートを開いた。大きな仕事をやり遂げた青柳さんは、これからは執筆の方に専念しようと、中学時代の友人も呼んでいた。ところが、ある著名な音楽評論家が、見当違いとも思える批評を新聞に発表したのだ。
実はドビュッシーは、オカルトに凝っていたり、エドガー・アラン・ポーの怪奇小説を好んでいたり、けっこうデカダン指向な人でした。しかし、音楽にはそういった要素は不要として、音楽ではあくまで耳に心地よい世界を表現した。そのあたりのねじれた所を理解していただけず……青柳いづみこは自分の演奏で自分のドビュッシー論を裏切った、というようなことが書いてありました。残念でした。でも、当時の日本の音楽界では、ピアニストがプログラムに文章を寄せることさえ厳禁というムードがあったのは事実です。ただ、あのおかげで今があるともいえるんです。だって、あまりに腹が立ち過ぎて、ピアノをやめそびれてしまったんですから(笑)。
ピアノを演奏することと、文章を書くこと。自身の心の充実を求めて選んだ道の両立に苦しんだこともある。
そんな姿を予見してか、安川先生の評伝『翼のはえた指』で第九回吉田秀和賞を受賞したお祝いの会で、知り合いの編集者たちの間で口論になったこともあるんです。「青柳さんは、ピアノを取るべきか、文章に専念すべきか」で意見が割れて(笑)。
なんだか、そんな行ったり来たり、浮いたり沈んだりの繰り返し。ずっと、そんなふうにやってきました。
そしてもう一つ。音楽の指導者・伝達者としての顔をのぞくと、さらに時代の先駆者の一面が強くなる。
音大の教壇に立っていたこともあるけど、それももう数年前に定年になりました。今は、一般の大人の人向けの音楽セミナーを、三十数年前からずっと続けています。私は、音楽を専門にやっていこうという人、例えば音大受験生の指導は向いていないんですよ。私の話を面白がって耳を傾けてくれる人に向けて、ピアノを通して気持ちを伝えるための弾き方、美しい響きの出し方、そんなことを教えられたらと思ってやっています。
あと、レクチャーコンサートのスタイルも昔からやってきたことですね。これも、今では珍しくなくなったけど、私が始めた頃は、珍しがられていたんですよ。その日演奏する曲の由来や背景、作曲家のことをお話ししながら、それもあわせて味わってほしい。それが、二刀流の私らしいコンサートかなと思っています。