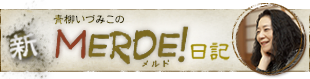二〇二五年三月二六日は、母方の郷里、兵庫県養父市のホールで開催された曹洞宗梅花流・御詠歌の大会にゲスト出演した。
祖母が曹洞宗の信者だったため、般若心経や修証義はよく唱えるのを聴いていた。唱えるだけでも節がつくが、御詠歌には数字譜で記載された旋律があり、ソロで歌ったり斉唱したり。
印象的なのは、歌い手たちが合間に鳴らす鈴。”すず”でも”りん”でもなく、”レイ”と読むと教えていただいた。
母の葬式も曹洞宗でお願いしたので、御詠歌を歌っていただき、鈴の音で涙がこらえきれなくなったおぼえがある。
三月二六日の大会は兵庫県北部のお寺の檀家さんたちによる奉詠会とのこと。事前に楽譜や音源を送っていただき、演奏曲目を考えた。
鈴の曲は思いつかなかったが、鐘の曲なら沢山ある。フランソワ・クープランのクラヴサン曲『シテール島の鐘』、カゼッラの『子供のための一一の小品』から「カリヨン」、「鐘」の別名で知られるラフマニノフの『前奏曲作品三-二』、ラヴェルの組曲『鏡』から「鐘の谷」。ドビュッシーの「沈める寺」にも、ブルターニュの海の底に沈んだ教会の鐘と僧侶の読経の声が出てくる。
午前中に少しリハーサルをして、一三時開始。美方郡、豊岡市、丹波市、丹波篠山市のお寺の檀家さんたちが次々に登壇し、正座される。
お作法が定められていて、合掌したあと、楽譜を開き、鈴をかまえて唱えはじめる。旋律はほぼ陰旋法なのだが、ときどき陽旋法になる。節を上下に震わせるあたりは、メリスマ唱法を思わせる。音程は、定められたものより少し高くとったり低く取ったり。平均律に慣れてしまうかえって難しいらしい。
ひとつのお寺さんが終わると講評があり、声の出し方、合わせ方、音程のとりかたなど細かく感想が述べられる。地元養父市からは永源寺さんと宗恩寺さんが合併で登壇。とてもよく声が出ていて、斉唱も揃って綺麗だった。
私の出番は一五時四〇分。子どもの頃から休みのたびに帰っていた故郷の思い出や祖母のことなど語りつつ、「鐘」にまつわるピアノ曲を弾いていった。皆さんとても熱心に聴いてくださり、気持ちのこもった演奏ができたように思う。
御詠歌の大会のあとは、車で三〇分ほど走り、神鍋高原の料亭「わらく」で打ち上げ。
地元のお酒、香住鶴で乾杯。大会の成功をお祝いした。
前菜はイノシシのローストや山菜のあえもの、地鶏の炙り焼き、するめ麹漬け、虹マスのおつくり(美味!)、名物の但馬牛のにぎり、イノシシの豆乳仕立て、里芋のスープ、陶板焼きは牛肉と鹿肉、肉厚の椎茸、あまごの塩焼き。
地元の食材を堪能したあと、〆は豆乳を練り込んだオリジナルのそばと焼きおにぎり茶漬け。
方丈さん(曹洞宗の住職のこと)たちのお話が興味深かった。曹洞宗といえば大本山の永平寺での厳しい修行が有名。日常生活から修行が始まるという考え方で、全てに細かい決まりごとがあり、一挙手一投足が管理される。睡眠も二~三時間で、寝床につく作法も細かく定められているという。
修行に行くときは、家族やご近所さんから出征前の兵隊さんのように万歳! で送られるとか。決死の覚悟なんですね。
学生時代、パリ音楽院の留学に赴く友人を空港まで見送り、万歳! で送り出したことを思い出した。あのころはドルも飛行機代も高く、一回行ったらなかなか戻って来れなかったから・・・。