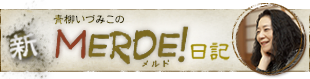井伏鱒二、上林曉、外村繁、村上菊一郎、木山捷平、太宰治……。中央線沿線に居を構える文士たちが集い、将棋を指し、酒を飲み、語らった阿佐ヶ谷会。
その会場となったのは、フランス文学者の青柳瑞穂の邸宅だった。祖父が終の栖(すみか)としたその家に現在も住み、二〇〇〇年から新阿佐ヶ谷会を続けている、ピアニストで文筆家の青柳いづみこさんに話を聞いた。
駅の南北をケヤキ並木の中杉通りがまっすぐに走るJR中央線阿佐ヶ谷駅。その整然とした印象とは裏腹に、阿佐ヶ谷は網の目に路地が広がる、奥行きのあるまちだ。狭小住宅の中に突然、立派な屋敷林が現れたかと思うと、鉄の外階段にバラが絡まる木造モルタルのアパートが健在だったりする。数えるほどになってしまったが、大正から昭和初期に建てられた木造家屋も残る。そのひとつが、フランス文学者で骨董蒐集家として知られる青柳瑞穂が終の栖とし、かつて中央線沿線に暮らす文士たちが集った「阿佐ヶ谷会」の会場となった家である。瑞穂の孫で、ピアニスト、文筆家として活躍する青柳いづみこさんはここで育ち、今も住まう。いづみこさんと同じまちに住むご縁から、青柳邸を何度か訪問しているにも関わらず、玄関の引き戸を開けるたびに胸が高鳴ってしまう。井伏鱒二や太宰治、上林暁といった人びとが、同じ戸を開け、灰暗い玄関のたたきを歩いた姿が浮び、青柳邸が醸し出すときの重みに圧倒されずにいられない。中央線沿線文壇サロンの舞台となった風景は現存するのだ。
井伏鱒二と青柳瑞穂の交流から始まった阿佐ヶ谷会。
昭和二年、瑞穂と井伏がそれぞれ、阿佐谷と荻窪(住所は現在の清水)に居を構え、交流を始めたことから阿佐ヶ谷会へと発展していった。
「『青柳君いるかね』と井伏はしばしば、それもひょっこり訪ねてきたそうです。清水から三十分ほどかけて歩いて来たんですね」といづみこさん。
阿佐ヶ谷会は昭和初期、沿線に住む文士たちによる阿佐ヶ谷将棋会として始まった。作家の小田嶽夫によれば、発起人として田畑修一郎、中山省三郎、そして本人の三名のほかに、「安成二郎、井伏鱒二、上林曉、外村繁、青柳瑞穂、村上菊一郎、木山捷平、中村地平、太宰治、亀井勝一郎、古谷綱正あたりだったと思う。みな東中野から三鷹辺までの住人で、時には中央線以外の住人で浅見淵、尾崎一雄、寺崎浩、石川淳などが参加したこともあったようである」(「阿佐ヶ谷あたりで大酒飲んだ−−中央沿線文壇地図」)
なぜ中央線沿いに文士が集まったのか。「家賃が安かった上に、貸家が多かったので家賃を踏み倒しやすかったこと。大正十二年の関東大震災で下町の家を焼け出されたこともあります。そして何より、井伏を慕い、私小説家たちが居を構えたということでしょう」(いづみこさん)
小田は同じ随筆で、「安成二郎が一番強くて、井伏鱒二、上林曉がこれに次いだ。(略)『将棋会』などと言うと、ひとかどの差し手の集まりのように取られるかも知れないが、その後十七、八年もたって、腕もいくらかは上がっている筈の井伏鱒二で八級ぐらいのものだから、他は推して知るべきである」と書いている。会場は、阿佐ヶ谷駅北口近くの将棋屋から碁会所、中国料理屋「ピノチオ」の離れへと移っていった。
青柳瑞穂邸が阿佐ヶ谷会の会場に。
集って将棋を指し、将棋をしない文士は採点付けや批評をし、終わると飲み会へと流れる。仕事の話はなしの、和気藹々とした親睦会だった。これが戦後になって、純粋な飲み会「阿佐ヶ谷会」へと発展していくのだが、青柳邸は、戦前の阿佐ヶ谷将棋会で数回、戦後のほとんどで会場となっている。
「瑞穂もそうでしたが、文士たちは赤貧でした。瑞穂の家には六畳と八畳間があり、骨董を蒐集していたので器も揃っていた。会を開くのに便利だったのです。当時の文士たちは勤めていないので、外に出なければ一人きりで篭り切りになってしまう。飲み屋で顔を合わせていたのでしょうが、月一回の阿佐ヶ谷会を心待ちにしていたという文士は多いですね」
そう話すいづみこさんからお借りした『青柳瑞穂と私』(山本任一(せんいち)、近代文藝社)によると、瑞穂をはじめ文士たちは、ちびた下駄に着流しの着物姿で、マントの肩が二重になったトンビをいつも羽織っていたという。山本任一は、瑞穂の義理の甥にあたり、東京の小学校、中学校に通うため青柳邸に寄宿していた。山本は月一度訪れるトンビの一団を、魔法使いだと思っていたようだ。
「皆、黙々と将棋を指し、酒も飲まず、文学論も戦わせることも無く、静かに帰っていった。(略)皆寝静まった夜半、突然玄関のガラスをどんどんと叩く声が響いた。(略)さっき帰って行った連中が、井伏御大を先頭にまた襲って来たのである。彼らは昼の会が果てた後、駅近くの赤提灯の幾つかで出来上がり、更に足りぬので再び叔父の家へと、とって返したのである。襖一枚のみ距てた八畳間からは、間も無く乱痴気騒ぎが聞こえて来た」(『青柳瑞穂と私』)
昔の文士はよく飲んだ。こんなおもしろい逸話も残っている。外村繁は、電話のない井伏に連絡を取りたいとき、そば屋に出前と共に「ピノチオで飲んでいる」などという伝言を頼んだという。電話はおろか、携帯もメールもない時代だからこそ、のんびりと、濃密な交流が持てたのだろう。
「阿佐ヶ谷文士たちに共通しているのは、純文学に徹して清貧に甘んじたということ、商業主義に陥ることをひどく嫌ったということだ。(略)文士たちはだから、交通費の工面すらままならぬことがあり、ようやくなけなしのお金をはたいて出版社まで原稿料を受け取りに行ったら小切手で渡された、それを換金するために銀行まで行く電車賃がないので、仕方なく歩いて行ったという笑えない話も伝わっている。
阿佐ヶ谷文士たちは、こういうみじめな日常生活を、それとは感じさせないほのぼのとした筆致で、できるだけのんびりしたような調子で書くところに味わいがあった。極限状態に身を置くことによく目が澄んできて、何気ない日常のものごとから人間の実存に迫る深い意味をくみとることができたのだろうか」といづみこさんは、『阿佐ヶ谷会文学アルバム』序文に書いている。
奔放な文士を支えた女たちの記憶。
阿佐ヶ谷文士たちに清貧の尊さを見る一方で、好き勝手に生きた文士を支えた女たちのことを、いづみこさんは忘れない。
子どもだった昭和三十年代、祖父の家で阿佐ヶ谷会が開かれていたものの、見ぬふりをしていた。瑞穂は金が入るとすべて骨董に注ぎ込み、家計の足しにはしない。妻のとよは「もう疲れてしまった」という言葉を残して亡くなる。これを機に、父と祖父は絶縁した。
男たちが開く阿佐ヶ谷会は、妻たちの家計に大きな負担を与えた。例えば、戦後復活第一回(昭和二十二年十二月)の阿佐ヶ谷会の会費は五百円。おかず一品を用意するようにとの申し伝えがあった。当時の五百円は、今なら三〜四千円だろうか。日々食べるものにも事欠く生活の中、夫の飲み代を捻出するために妻たちは、着の身着のままで質屋通いをした。外村の妻は、戦後復活第一回の阿佐ヶ谷会の数週間後に倒れ、十ヵ月の闘病の末に亡くなった。
上林の妻もかろうじて一日一日をやりすごしていたが、精神に異常をきたすようになり、亡くなっている。上林本人が脳溢血で倒れた後、介護をしながら口述筆・記をしたのは妹だった。幼いいつみこさんは父と祖父が断絶しているなかでも、祖父の家に出入りしている。
「祖父の酒の肴だったカラスミをつまみ食いしたり、祖父の書棚から海外文学の翻訳物をずいぶん読みました。阿佐ヶ谷会に顔を出すようなことはありませんでしたが、庭から覗くと、祖母が亡くなったあとの阿佐ヶ谷会では、玄人といった感じの女将たちが台所を手伝っていて、きれいだなあ、と思ったものです」
阿佐ヶ谷文士や瑞穂について、冷静な見方をするいづみこさんだが、瑞穂の「真贋を見抜く眼と姿勢」には一目を置いている。瑞穂は、鎌倉時代の古い能面、平安時代の自然紬の壷など、骨董狂でも一生に一度出合えるかという名品をいくつも探し当てた。中でも青梅街道沿の古道具屋で、格安で手に入れた尾形光琳筆の軸物は、後に光琳唯一の肖像画「中村内蔵助像」と判明し、重要文化財になっている。
「祖父は、良いものを見ると、身体が震えたそうです。誰かの後追いではなく、自ら本物を見極める。そうした祖父の眼を井伏や太宰は尊敬し、時に怖れていました。祖父と違い私は音楽家ですが、誰の意見でもなく、自分の目と耳で優れたピアニストを見極めることを大事にしています」
瑞穂の評伝の出版を契機に結成された新阿佐ヶ谷会。
二〇〇〇年九月、いづみこさんは、祖父の評伝『青柳瑞穂の生涯真贋のあわいに』(新潮社、のちに平凡社ライブラリー)を上梓した。書評家の岡崎武志さんが、その本についていづみこさんをインタビューしたことがきっかけとなり結成されたのが、「新阿佐ヶ谷会」である。岡崎さんは、阿佐ヶ谷文士の中でも木山捷平が特に好きで、いつか伝説の会場の中に入りたいと念じていたのだという。
新阿佐ヶ谷会の第一回は、二〇〇二年一月四日。出席者は、岡崎さん、上林暁の初版本を蒐集している新潮社の八尾久男さん、太宰治について長年研究を続ける萩原茂さん、中央線沿線の文士に関する著作もある文芸評論家の川本三郎さん、白水社の編集者で梅崎春生ファンの小山英俊さん、フランス文学者の野崎歓さん、筑摩書房で決定版『上林暁全集』を編集した山本克俊さん、装幀家の間村俊一さん、そしていづみこさんの総勢九名。会場は青柳邸の六畳間で、シャンパン一本、四升の日本酒と一升の焼酎が空になったというから、新阿佐ヶ谷会も大酒飲みの一団だ。
二〇〇三年六月には、昭和十七年に行われた「阿佐ヶ谷会奥多摩編」を再現し、御嶽渓谷を散歩し、玉川屋というそば屋で懇親会を開いている。その後、将棋を指すかわりにピアノを弾いてから酒を飲む会を、年一度続けている。
「岡崎さんは古書、野崎さんは映画、川本先生は日本映画がお好きで、私は音楽が専門。多分野のメンバーなので、話が思いもよらない方向に、おもしろく発展していくんです。たぶん、瑞穂たちの阿佐ヶ谷会よりも話題が広いと思います。コロナ禍で中断していていましたが、二〇二二年に再開しました。ほとんどが無名で、お金がないのに時間はあった昔の阿佐ヶ谷文士と違って、新阿佐ヶ谷会のメンバーは売れっ子ばかり。月一回は無理ですが、可能な限り続いてほしいですね」
会って、食べて、飲んで、語らう。
いづみこさんが二〇二〇年十月に出版した『阿佐ヶ谷アタリデ大ザケノンダ 文士の町のいまむかし』のなかに
ある文士から、祖父の瑞穂といづみこさんの横顔が似ていると言われた、という件がある。今回、瑞穂のさまざまなポートレートを眺め、確かにそうかもしれないと思った。祖父にならって「新阿佐ヶ谷会」を開くいづみこさんは、中央線沿線のいきつけの店で、「会って、食べて、飲んで、語らう」ことも好む。
阿佐ヶ谷文士の時代と違い、誰もが忙しい。ネット環境の発達で、リアルに会わずとも、会話ができる状況になっている。阿佐ヶ谷会や新阿佐ヶ谷会のような、サロン文化が生まれるのは難しいのだろうか。それでもあのバーに行けば写真家や写真好きに会える、あのカフェには古本好きが集まっている、あの居酒屋に行けば文学や映画の話ができる、という店をいくつか思い出すことができる。中央線沿いにはサロン文化が根づいている、と信じたい。
/////////////////////////////////////////
P-2
昭和29年5月22日の阿佐ヶ谷会。
左から一人おいて外村繁、小田嶽夫、木山捷平、上林曉、中野好夫、瀧井孝作、青柳瑞穂、河盛好蔵、火野葦平、辰野隆、井伏鱒二、蔵原伸二郎
(提供・青柳いづみこ以下記述のないものは同様)
===========================================
P-3
上・阿佐ヶ谷会での井伏鱒二(左)と上林曉(右)の対局。
観戦するのは、青柳瑞穂と外村繁。昭和28年3月11日撮影。
下・阿佐ヶ谷会で使用された青柳瑞穂の将棋盤
===========================================
P-4
昭和17年2月5日、阿佐ヶ谷会御嶽ハイキングの途上、御嶽橋の上で。
右から浜野修、上林曉、太宰治、青柳瑞穂(撮影・安成二郎)
==========================================
P-5
阿佐ヶ谷会の開催を知らせる通知。「会費七百円」とある
===========================================
P-6
井伏鱒二から青柳瑞穂宛に送られた、骨董についての意見を求める手紙
===========================================
P-7
岡崎武志さんが描いた、2005年1月9日新阿佐ヶ谷会出席者の似顔絵色紙
===========================================
P-8
2003年6月に新阿佐ヶ谷会で行った奥多摩御嶽渓谷ハイキングの冊子。
絵・岡崎武志、装幀・間村俊一
**********************************************
金丸裕子・文
text by Yuko Kanamaru
かなまる ゆうこ
ライター、編集者。取材と執筆を担当した本に『カコちゃんが語る植田正治の写真と生活』『黒田泰蔵白磁へ』など。近著に『自由が丘画廊ものがたり戦後前衛美術と画商・実川暢宏』。
泉大悟・写真
photographs by Daigo Izumi