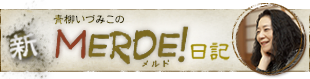フランスの作曲家で猫好きで知られるのは、2025年3月に生誕150年を迎えたモーリス・ラヴェル(1875-1937)だろう。ラヴェルはムー二とミヌーという2匹のシャム猫を飼っており、くわえたばこでムーニを抱えている写真が残っている(猫はけむたくなかったろうか?)。当時のフランスでは、シャム猫はまだまだ珍しかったという。
ママっ子だったラヴェルは、1917年に母親が亡くなってからは何も仕事ができず意気消沈していた。一人でいるのが寂しくて、弟のエドゥワールや友人の家を転々としていた時期もある。
1921年5月、46歳になったとき、パリから南西50キロにあるモンフォール・ラモリー村の丘の上の一軒家に移り住み、「ベルヴェデーレ荘」と名づけた。ラヴェラと親しかったヴァイオリニストのエレーヌ・ジュルダン・モランジュによれば、「ブリー・チーズの4分の1を道端に置いたような」家で、おもちゃ箱のように可愛らしい展望台と日本風の庭園がついていた。シャム猫の一家はこの家に住んでおり、ムーニの名付け親はエレーヌだつた。
彼の親指はすぐ関節がはずれたようによく動き、指先は少し角張っていたが、こ
んなピアニストらしい筋肉質の手で不器用に撫でまわしては猫たちを悩ました。
(『ラヴェルと私たち』)
エレーヌによれば、ラヴェルはよく「猫」流の手紙を出したそうだ「ムーニにあなたのお言葉を伝えておきました。あなたの鼻の頭をお嘗めいたします」
当時ラヴェルは『子供と魔法』というオペラの作曲中だった。台本作者は、『雌猫』というタイトルの小説も書いているコレット。『子供と魔法』の中にも、猫たちの二重唱が出てくる。コレットは、黒猫と白猫の鳴き声について、ラヴェルから「ムアオというところをムエーンという言葉にしたら、あるいはその反対のことをしたらまずいですか?」と相談されたという。
あるとき、エレーヌとラヴェルがこの猫たちの二重唱を口ずさんでいたら、猫たちの一家が目をまんまるにして集まってきた。どうやら自分たちの他にも猫の家族がいると思ったらしい。エレーヌは、「ラヴェルは猫のまねの異常な才能であると言わねばなるまい」と書く。
猫の鳴きまねと言えば、フォーレのピアノ4手連弾曲『ドリー』の「mi-a-ou(ミ・ア・ウ)」を思い浮かべる。ところがこれは出版社の勘違いで、実際には「Messieu Aoul!」だったという。
『ドリー』は当時フォーレを庇護していたエンマ・バルダックの娘エレーヌ(通称ドリー)に捧げられた作品で、「ミ・ア・ウ」は彼女の2歳の誕生日を祝うために書かれた。幼いエレーヌが兄のラウールを呼ぶのに、このように発音したことから名づけられたらしい。
『ドリー』にはもうひとつ、「Kitty-valse(キティー・ヴァルス)」という曲もあり、こちらはエレーヌの4歳の誕生日に贈られた。これまた猫のワルツのように読めるが、実は、ラウールが飼っていたケティという犬の名前を冠して「Ketty-Valse」と名づけたのに、またまた出版社に勘違いされてしまったらしい。つまり、『ドリー』には猫が不在、という奇妙な事態が起きたわけだ。
奇妙な事態ついでにもうひとつ余計なエピソードを。
サロンの歌姫エンマ・バノレダックはボルドーのモイーズ家の生まれで、17歳で富裕な銀行家と結婚したものの、名のある作曲家と結婚して後世に名を残すという野望にかられていた。彼女はまずフォーレに近付き、あまり裕福ではない彼を広大な別荘に招いて作曲に専念させ、そこで生まれたヴェルレーヌの詩による歌曲集『優しい歌』を自宅のサロンで初演している。長男のラウールは1881年生まれだが、『ドリー』を捧げられたエレーヌは92年生まれで、ちょうどフォーレとエンマが一番仲がよかった時期に当たる。
音楽学者のジャン・ミシェル・ネクトゥーは『評伝フォーレ』の中で「ドリー・バルダックはフォーレの娘だと、時折、囁かれていたが、ほぼそのことに間違いはないだろう」と書いている。碩学で知られるネクトゥがそう言うのだから間違いないのだろう。
エンマの次のターゲットはラヴェル。パリ音楽院でフォーレのクラスに学び、仲間のシャルル・ケクラン、ロジェ・デュカスとともにシャンゼリゼ近くのエンマのサロンに出入りしていた。ラヴェルと親交のあったピアニストのリカルド・ビニェスや詩人のレオン・ポール・ファルグ、トリスタン・クリングゾルなど、のちに「アパッシュ」(アパッチのフランス読み。新しい芸術を庇護する「ごろつき」の意味)と呼ばれることになるメン
バ一も集った。
ラヴェルが1903年に書いた『シェーラザード』は声楽とオーケストラのための作品で、トリスタン・クリングゾル(ワーグナーの楽劇の登場人物をつなぎあわせたものすごい筆名だ……)のテキストにもとづいている。エンマに捧げられた第3曲「つれない人」は、「若く美しい男が女性の家の前で歌うものの、家に招じ入れようとすると見向きもせずに立ち去る」という内容で、実際に起きた(であろう)ことが反映されている。クリングゾルはエンマについて、次のような意味ありげなコメントを残している。
大変才能があって、また抜け目のない某女流歌手が、(ラヴェル)に目をつけた。
彼女は自分のヘブライの……で損をした。彼女は仕方なくもうひとりの別の芸術
家で我慢した。
この「我慢した」のがドビュッシーだったというわけだ。エンマは息子のラウールをドビュッシーに弟子入りさせてコンタクトを取り、サロンに出入りしていたケクランのピァノでドビュッシーの歌曲を歌い、息子を通して自宅に招き……と徐々に距離を縮める。
すっかりからめとられたドビュッシーは、1904年6月、妻が実家に帰っているのを良いことにエンマを自宅に招き……7月末、二人はジャージー島に駆け落ちしてしまう。
1905年10月にはシュシュという可愛い女の子が生まれ、一家は高級住宅街で知られる16区に一軒家を借り、ドリーやエンマの実母も同居する生活がはじまる。その贅沢なお屋敷の玄関前で、ドビュッシーが2匹の犬と写っている写真が残っている。大きくて毛並みが長く、尻尾も長く、堂々とした犬と、小さくて毛が短く、尻尾も短く、愛嬌のある犬。
ところでドビュッシーは、若いときは猫派で、リリーヌという「毛が灰色の、半アンゴラ種」の猫を飼っていた。最初の妻との家庭でも2匹の猫を飼っていたという。「夫妻は何でも猫たちのしたい放題にさせていました」とピアノの生徒は回想している。「自分たちの主人のように物静かな猫たちは、書物机の上におごそかに陣取り、そうしたければ、鉛筆を散らかす権利を持っていました」
ドビュッシー自身が猫に似ていたようだ。1890年代はじめ、象徴派のコロニーのような書店〈独立芸術書房〉で彼を見かけた詩人のアンリ・ド・レニエは次のように描写している。
彼は音を殺して重たげな感じの、独特な足どりで入ってきた。やわらかくて無頓
着なあの体つきが、目に浮かぶ。あおざめて冴えぬいろの、あの顔。重い瞼の内
側で黒い瞳がいきいきとしている、あの目。長い縮れ毛を垂らしてかくした、異
様につきでて広いあの額。猫のような感じでいながらジプシーみたい、火のよう
に燃えていながら沈潜しているあの風貌。(平島正郎『ドビュッシー』)
その10年ほど前、ドビュッシーはモンマルトノレの文芸酒場〈黒猫〉の常連だった。1881年末、ロシュシュアール通り84番地に開店した第一次〈黒猫〉は、デカダンの巣窟と呼ばれた。命名はエドガー・ポの『黒猫』からきているという説と、店主のサリスが建物の庇の下に一匹の黒猫を見つけたからという説がある。いずれにしてもウリは黒猫で、看板には三日月に尻尾をかけた黒猫が描かれていたし、開店間もなく刊行されたタブロイド紙『黒猫』でも、LE CHAT NOIRという題字の下で、アンリ・ピールの描く黒猫が尻尾をぴんと立てている。
〈黒猫〉は、モンマルトル界隈で初めてピアノを置くことを許可された酒場だった。酒を出すカウンターのうしろには、中心に猫の頭が彫刻された巨大な金色の太陽が掲げられ、そばにアップライトのピアノが置かれていたという。ドビュッシーは、パリ音楽院の学生時代からここに通い、デカダン詩人のモーリス・ロリナや作曲家のフラジュロル、詩人兼作曲家のポール・デルメやマリ・クリジンスカらとともに「鍵盤を叩きながら歌った」。
〈黒猫〉は1885年にヴィクトル・マッセ街に移転する。今度は一軒家で、エミール・グードーの散文集『青い紙片』によれば、「建物の正面には途方もなく大きな鉄細工のランプが2つあり、その間の金の太陽の前で巨大な黒猫が日向ぼっこしていた」という。
第二次〈黒猫〉の目玉は、アンリ・リヴィエールが制作した「影絵芝居」だった。当時の絵を見ると、壁にはめ込まれたスクリーンには丸い枠がつき、翼のある黒猫が観客を見下ろしている。
2025年7月に没後100年を迎えるエリック・サティが第二次〈黒猫〉を訪れるのは、1887年末のことである。フラジュロルが作曲した『聖アントワーヌの誘惑』を見たサティは、ほどなく第2ピアニストに雇われ、自分も「影絵芝居」の伴奏で日銭を得るようになる。1891年からは同じモンマルトルの〈オーベルジュ・デュ・クルー〉に移るが、稼ぎはじゅぶんではなく、1896年には債権者に追われて「戸棚」と呼ばれた極小の部屋に引っ越し、さらに98年に郊外のアルクイユの「4本煙突の家」に移る。相変わらずモンマルトルの酒場でピアノを弾いていたが、電車賃がないため、徒歩でパリに向かう日も多かった。以降、亡くなるまで自宅に誰も立ち入らせなかったサティだが、動物だけは例外で、餌をやるために迷い犬や捨て猫を何度となく連れ帰ったという。
ドビュッシーは猫の音楽を残していないが、サティは1923年5月、亡くなる2年前にレオン・ポール・ファルグの詩による歌曲集『潜水人形』で「猫の歌」という短い曲を書いている。歌詞は”Il est une bébête/Ti Lipetit n’enfant”ではじまる。「ティ・リ」は猫の名前、「bébête」は「赤ちゃんbébéと「動物bête」のかけ言葉。「ニャンファン」はenfantを猫語にしているのだろうか。『潜水人形』は5曲からなり、1曲目が「ネズミの歌」、5曲目が「猫の歌」というのもおもしろい(なぜ反対ではないのだろう??)。