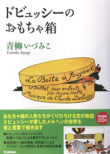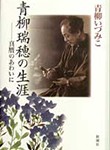書評
【書評】「花を聴く 花を詠む」(西日本新聞 2021年12月26日)
カリスマ書店員の激オシ本 丸善博多店 徳永圭子さん 青柳いづみこ著『花を聴く 花を詠む』 切なく浮かぶ色、香り、毒 ピアニストで文筆家の著者が花をモチーフに古今東西の文学や音楽にまつわる記憶を鮮やかに紡いだエッセイ集。…
【書評】「阿佐ヶ谷アタリデ大ザケノンダ」(武蔵野樹林 2021年 vol.7)
関東大震災後、貧乏な文士たちが中央線沿線に越してきた。筆頭は『荻窪風土記』の井伏鱒二。彼を中心として、「阿佐ヶ谷会」が起こり、将棋会や宴会などが催された。会場の一つは、著者の祖父であり、フランス文学者・骨董蒐集家の青柳瑞…
【書評】「阿佐ヶ谷アタリデ大ザケノンダ」(西日本新聞2021年2月6日付朝刊)
戦前・戦後の東京には阿佐ヶ谷・馬込・田端などに文士村というものが存在し、小説家や文芸評論家、あるいは音楽家や編集者などさまざまな芸術家が集い刺激し合っていた。本書はその阿佐ヶ谷に住むフランス文学者の青柳瑞穂の家に集まる人…
【書評】「阿佐ヶ谷アタリデ大ザケノンダ」(産経新聞2021年1月17日)
文化根付いた青春の匂い JR中央線沿線、中野から吉祥寺にかけては、若者に優しい町である。私自身そうだったように、多くの地方出身者は、この地域に住むことで少しずつ「東京」になじんでいった。 中央線沿いに金のないミュージシャ…
【書評】「阿佐ヶ谷アタリデ大ザケノンダ」(読売新聞2020年12月6日付朝刊)
阿佐ヶ谷文士といえば戦前、東京の阿佐谷周辺に居を構えた井伏鱒二や太宰治、外村繁、河盛好蔵、亀井勝一郎らが思い起こされる。その集まりは文学論議を交わす清談の会と思っていたが、真相は井伏の詩から取った本書のタイトルのごときだ…
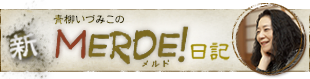
書籍関連 最新5件
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(読売新聞 2025年9月14日)
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(東京新聞 2025年10月25日)
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(図書新聞 2025年9月27日)
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(京都新聞 2025年9月14日)
- 【関連記事】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(秋田さきがけ 2025年9月1日)
Pick Up!
書籍のご注文
サイン入り書籍をご希望の方
ご希望の方には、青柳いづみこサイン入りの書籍をお送り致します。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上お申し込みください。
お支払い方法:銀行振込