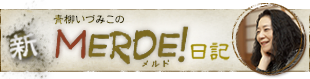熱く通った天才同士の友情
評・青澤隆明 (音楽評論家)
サティが亡くなったのは1925年7月、今から100年前の夏だった。フランス芸術史上の奇才で、さまざまな音楽実験の先駆者ともみなされる偉才だ。
4歳年長の友人ドビュッシーは、その7年前の春に没した。「私は創造者としての彼の進化のすべてに立ち会った」とサティは書いた。「『四重奏曲』『ビリティスの歌』『ペレアスとメリザンド』は私の目の前で生まれた」と。独尊の天才同士は若くして出会い、互いを啓発し、やがて仲たがいしたまま、世を去った。
残されたものは第一に作品、それから本人や周囲の証言であり、それぞれの立場からの毀誉褒貶(きよほうへん)だ。「ドビュッシーは何も見出さなかった。すべてはサティが考えたのだ」といった見解さえも広く流布されたほどに。
後から乗る者は、自分の都合により、先達の肩を持ったり、弾劾したりする。美学や思潮の歴史も多くはその繰り返し、振幅と変容のうちにある。
この場合、サティを称揚することを利としたのは詩人コクトーのようだ。新しさがモダニズムの旗である以上、新旧は大きな問題になる。年下のラヴェルもピアノ曲のアイデアを盗用されたとして、ドビュッシーに敵対する。取り巻きや周囲が事を大きくするものなのだ。
さて、1980年代からドビュッシーを研究してきた著者は、本書で二人の関係の検証を試みる。35年前後にわたる交友や創作、関心事をたどる推理の道行きが時代順につづられて本書の核となるが、結果としてフランス近代の芸術思潮が描かれている。が、両者の出会いの時期にしても特定することはできない。
しかし、今の私たちにとっては、影響の力学よりも各自の創作が遺された事実の方が重要だ。そして、敬愛と友情が、たとえ近親増悪に近いものであっても両者に熱く通っていたということが。付録の著者対談で、高橋悠治が年上の武満徹に複雑な感情を抱きつつも「かけがえのない友だちでありつづけた」ことを語る言葉がいたく心に響くように。