書評
【書評】音楽で生きていく! 10人の音楽家と語るこれからのキャリアデザイン(WEB音遊人 2020.2.6)
10人の音楽家による「成功の秘訣」をまとめた『音楽で生きていく!』は、演奏家、指揮者、作曲家、さらには三弦奏者も含む多彩な顔ぶれの若き音楽家たちのインタビュー集だ。日頃は音楽で思いを伝えている表現者たちが、みずからのキャ…
【書評】音楽で生きていく! 10人の音楽家と語るこれからのキャリアデザイン(月刊ピアノ2020年1月号)
プロはどうやって道を切り拓いたのか ピアニストと文筆家の両面で活躍する青柳いづみこが、現在もっとも輝きを放つ20〜30代の音楽家と”キャリアデザイン”をテーマにトークした対談集。登場アーティストは、會田瑞樹(打楽器)、上…
【書評】音楽で生きていく! 10人の音楽家と語るこれからのキャリアデザイン(ハンナ2020年1月号)
音楽大学を卒業して、音楽を仕事として生きていく。音楽大学に入る多くの人が夢見る世界だが、それを実現できるのはほんの一握りだけだ。そのほんの一握りは、他と何が違うのか? 生まれ、家庭環境、思考…。成功を勝ち取るための戦略を…
【書評】音楽で生きていく! 10人の音楽家と語るこれからのキャリアデザイン(ステレオ2020年1月号)
ピアニストであり文筆家でもある著者が、既成の概念にとらわれない活動を展開している。いまもっとも輝きを放つ20〜30代の演奏家10人とキャリアデザイン(目標を設定してそれに向かった生き方を設計していくこと、自分の仕事と人生…
【書評】音楽で生きていく! 10人の音楽家と語るこれからのキャリアデザイン(ショパン2020年1月号)
ピアニストであり文筆家の青柳いづみこさんが、夢を実現して成功の道を歩む20〜30代の若手音楽家たちと対談。”キャリアデザイン”について家庭環境や様々な挫折、ターニングポイントなど、とことん追求した1冊だ。登場するのは田村…
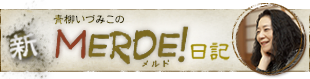
書籍関連 最新5件
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(読売新聞 2025年9月14日)
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(東京新聞 2025年10月25日)
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(図書新聞 2025年9月27日)
- 【書評】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(京都新聞 2025年9月14日)
- 【関連記事】『サティとドビュッシー先駆者はどちらか』(秋田さきがけ 2025年9月1日)
Pick Up!
書籍のご注文
サイン入り書籍をご希望の方
ご希望の方には、青柳いづみこサイン入りの書籍をお送り致します。
ご注文フォームに必要事項をご記入の上お申し込みください。
お支払い方法:銀行振込


