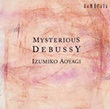高橋悠治と連弾でCD「春の祭典」をリリース
青柳がプリモ(高音)で悠治がセコンド(低音)
「ストラヴィンスキーの仕掛けがよく分かります」
1913年5月29日、シャンゼリゼ劇場で行われたバレエ「春の祭典」の初演は、音楽史に残る事件となった。複雑なリズムや不協和音に耐えられない聴衆と受け入れた観客の殴り合いのけんかが始まってしまった。
ストラヴィンスキーはこの管弦楽曲とともに連弾(4手ピアノ)版も書いた。青柳いづみこのライナーノーツによると、初演の1年前、評論家ルイ・ラロアの別荘で、ドビュッシーとともに連弾している。また、高橋悠治は1968年、タングルウッド音楽祭で指揮者マイケル・ティルソン・トーマスと演奏している。
「悠治さんは、私の学生時代は雲の上の存在でした。2014年に連弾に誘っていただいたのですが、日本人作品はだめ、オーケストラの連弾版は弾きたくない、となかなか決まりませんでした。昨年秋のHAKUJUホールで、『春の祭典』をやりましょうということになり、半年間、合わせました。最初のうち私は変拍子が落ちまくって大変でしたが、辛抱強く練習につきあってくださった」
2人の演奏法、音楽への向き合い方、ピアニズムは全く違う。作品を仕上げるまでが大変だった。
「リズム感、呼吸、フレーズに対する考え方などいっぱい衝突しました。矢代秋雄先生にスコア・リーディングを習いましたから、さまざまな楽器の音色を作ろうとタッチを工夫すると、悠治さんはオーケストラをなぞる必要はない、と拒絶するのです。衝突しながらも互いの言うことの意味を考え、歩み寄っていった感じです」
悠治がセコンドで低音とペダルを受け持ち、青柳がプリモで高音を受け持った。アンサンブルの考え方も違った。
「イニシアチブを握るのはセコンドです。私はフランスでコレペティトーアをしていたので、合わせなければと思うのですが、悠治さんは予定調和が嫌い。お互いのパートを聴いていない訳ではないのですが、あえて合わせる必要はないというスタンスです。私にとって練習するということは解釈を固定化するのではなく、その場その場の霊感に自在に対応するためです。自由になりたいのはみな一緒なのですが、その手順が違いました」
青柳はドビュッシーのスペシヤリスト。ドビュッシーは「ペトルーシュカ」は気に入り影響も受けたが『春の祭典』は怖い、と感じていたそう。
「連弾で演奏すると、ストラヴィンスキーの仕掛けがはっきり分かります。『春の祭典』の残酷なところ、『ペトルーシュカ』の人形の悲しみがひしひしと伝わります。私も弾き込んで分かりました。音楽の地平線が広がった感じです」