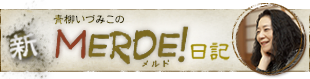近代フランス音楽の精華をめぐって
著者の長年にわたる演奏経験と積み重ねた博識
昼間 賢
本書は、本邦一のドビュッシー研究家、かつ名著『ドビュッシー 想念のエクトプラズム』一九九七年刊(文庫改定版、二〇〇九年刊)の著者であり、戦間期のパリで音楽教育を受けた安川加壽子直系のピアニストでもある青柳氏が、おそらく満を持して、ドビュッシーの好敵手だったサティとの比較諭に着手した好著である。好敵手だった、そう言っていいかどうか、ドビュッシーの、サティの、そして双方のファンにおいては脳裏に雲がかかるだろう。著者はその多様な映めを戴断することなく、その生成過程を十分に再現し、その魅力を思う存分語り、提示している。
本書冒頭で「もちろん〈ドビュッシー派〉である」と宣言する著者に、あるとき「サティに目を開かれた」機会が訪れた。「二〇一六年に(中略)高橋悠治が弾く『三つのサラバンド』を聴いたときだった」と。これまでは、サティより四歳年上であり、現実にも先輩音楽家として影響を与える側に置かれがちだったドビュッシーだが、一八八七年に作られたこの曲を介して見ると、逆に後輩から、重要な影響を受けていたかもしれない(自身も後に同名の曲を作っている)と、著者は高橋の演奏において決足的に気づく。決定的に、とは、すでにイギリスの音楽学者オーリッジが同様の指摘を自身のサティ論においてなしているのを、著者は研究者として知ってはいた。そこへ、ということで。この新発見から著者は著述を始める。
実は「先駆者はどちらか」問題は、新しさを錦の御旗とする近代芸術においては、しばしば起こるのが必然的な、宿命と言ってよい問題であった。他では、詩人アポリネールが主導的だったフランス現代詩の黎明期に、アポリネールより七つ下のサンドラールが長編詩『ニューヨークの復活祭』でもって詩の可能性を広げた、にもかかわらず、その功績が、サンドラールの求めに応じて助言を与えたというアポリネールに帰せられてしまった、サンドラールは悲憤し後悔した、という逸話を思い出される。
ドビュッシーかサティか、においては、問題はより複雑である。すなわち、彼らが活躍した当時、音楽史に新しさをもたらした者は明らかにドビュッシーだった、が、彼らの没後、つまり現在においては、必ずしもそうとは言えない。そうした見方がこの百年間に広がり、定まりつつある。この対比は、「クラシック」最後の新しさ対「現代音楽」最初の新しさ、こう要約できるだろう。事実、本書にも記されているとおり、ドビュッシーの名声に対してサティ過小評価是正の契機となった一九一一年一月の「独立音楽協会」主催のコンサートでは、同会発起人の一人ラヴェルが、サティ作品公演のプログラムにおいて、当時演奏されもした「サラバンド第二番」の意義を特筆している。これ以降、第一次大戦前後のおよそ十年間は、遅まきながら、サティが音楽界の中心人物になる。
ところで、最初に着手し上梓した訳書が『エリック・サティの郊外』だった評者は、したがってサティ派を自認する一人だが、本書を読んで、その主題−−先駆者はどちらか−−とは別に、ドビュッシーがサティより優れている点を、著者のある指摘によってはっきり知ることができた。それは、この見解「劇作品における音と言葉のかかわりにおいて、ドビュッシーとサティには決定的な差異があると思う」(本書一五三頁)である。
周知のとおり、サティには『ジュ・トゥ・ヴー』や『優しく』など、今日でも時折演じられるシャンソンの名曲がある。それらは、良い旋律をピアノで伴奏する式の、通常のポピュラーソングだ。それに対して、ドビュッシーの歌は歌曲(原語メロディー)、すなわち音と言葉の関係が考え抜かれ、非常に繊細な手つきで作られた小品群である。特に、ちょうど音楽界の新旧が交代しつつあった一〇年がら一一年の時期に作曲された『フランソワ・ヴィヨンのバラード』は、自身のオーケストラ版も含めて、ドビュッシー後期の傑作である。歌劇『ペレアスとメリザンド』の成功と対照的に、その深化でもあった晩年の歌曲は、拍節を備えた音楽には合いにくいフランス語の詩を見事作品化した技法がフランス語話者以外にはわかりにくいため、十分評価されていないのが残念というか、もったいないと思われる。ドビュッシーの「鋼鉄のような明解さには、反ドビュッシー的な反動さえ歯が立たない」と述べるフランスのある哲学者は、ドビュッシーを「〈フランソワ・ヴィヨンのバラード〉の作曲家」と言い換えた上で、その特質を「サティの厳しいまでの簡素さを含めて、ストラヴィンスキーの形式上の厳格さ、ルーセル、プロコフィエフ、ミヨー、タンスマンの力強さをも完全に予見したほどである」としている(ウラジミール・ジャソケレヴィッチ『ドビュッシー 生と死の音楽』原書一九六八年刊)。『ヴィヨンのバラード』の素晴らしさは、まさに青柳氏が伴奏を務め、ソプラノに盛田麻央を迎えた好演が、有名動画サイトの氏のチャンネルで公開されているので、是非ご視聴あれ。
結局のところ、どちらが先駆者だったかは局面による。彼ら二人のきわめて豊かな音楽遺産をどの観点から再訪するかによる。そんなことは承知の上で、著者は長年にわたる演奏経験と積み重ねた博識によって本書を著した。それでいて、衒学的な調子などなく平易な言葉遣いで書かれているのも、著者のファンにはおなじみの魅力だろう。サティ没後百年に当たる本年、これから迎える読書の秋に、お勧めの一冊である。