|執筆&インタビュー|MERDE日記 |新MERDE日記 |お問い合わせ|
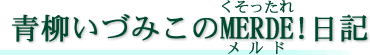
|
|トップページ| プロフィール |コンサート|CD|書籍| |執筆&インタビュー|MERDE日記 |新MERDE日記 |お問い合わせ| |
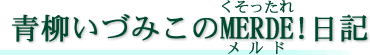 |
2005年4月10日/朝日新聞の書評委員 2002年4月から始めた朝日新聞の書評委員も、予定通り3年目で任期満了。 きっかけは、同じ朝日新聞の「本屋さんに行こう」という欄に登場したことだった。行きつけの本屋さんに行って目に止まった本を購入し、その様子を記者さんが取材し、カメラさんが写真を撮る。 私は、新刊書店にしては変な本が並んでいることで有名な南阿佐ヶ谷の「書原」に行き、『グレン・グールドの演奏術』とか団鬼六のエロ本とか、若桑みどりさんの美術書とか、岡崎武志さんの『古本のすすめ』とか、例によって脈絡のない本を購入し、家の前のざくろの木のところで、それらの本を手にとっている写真を撮ってもらい、取材は終了かと思ったら、喫茶店で記者さんが、実は・・・と切り出した。 「書評委員になっていただけませんか?」 期間は3年、大変だったら1年でやめてもよい。条件はけっこう厳しくて、任期中は委員の本は書評の対象にならない。 よくわからないので、ちょうど本を出すことになっていた白水社の編集者に相談した。「朝日の書評は本が一番動くので、書評にとりあげられないのは痛いけれど、青柳さんは文筆関係者や出版関係者に知り合いが少ないから、つきあいの範囲が拡がって、長い目で見たらいいことがあるでしょう」とのこと。 ついで、直前まで書評委員をつとめていらした哲学者の木田元先生にお電話した。書評委員になって一番大変なことは? ときくと「本が溜まって困ること」という返事が返ってきた。各出版社から書評用の献本が山と送られてくる。幸い、木田先生のお宅は子供たちが巣立って一部屋あいていたので、そこに置くことにした。1年たつと部屋がいっぱいになる。年末にそれらを、元勤務先の大学の図書館用、郷里の図書館用と分けて箱に詰め、発送する作業だけで2、3日かかった・・・というようなお話。 私の家の郵便ポストは小さいので、山なす書籍小包がはいらないかもしれない、もっと大きいのに買いかえようか、と主人と相談したが、まあ、様子を見てから、と思っていたら3年たってしまった。私は音楽家なので、文芸関係者や執筆関係者の名簿には載っていないらしい。年に10回しか行かない大阪の音大に本が送りつけられたりもしたが、本当に本が山と届くようになったのはやめる半年前ぐらいからだった。書評家として認知してもらうのに2年半ぐらいかかったということか。 書評委員会は隔週の水曜日、浜離宮朝日ホールのビルの上の会議室で開かれれる。6時から選書で7時から委員会。朝日新聞社の最寄り駅は都営地下鉄大江戸線。私の家からは、けっこう行きにくい。最初のうちは地下鉄丸の内線の中野坂上、あるいはJRの代々木から大江戸線に乗り換えていたが、2年目ぐらいから面倒臭くなり、JRで新橋まで行ってワンメーターでタクシーに乗るようになってしまった。出無精の私は支度に時間がかかり、出ようと思っていると財布が見つからなかったり、毎回家を出るのが6時前、息せき切ってかけつけるという状況がつづいた。 会議室には、記者さんたちが選んだ100冊ぐらいの本が並んでいる。最初の方が文芸書、ついで翻訳書、歴史やノンフィクション、科学書などが並び、真ん中ぐらいが政治・経済の本、最後は音楽や美術、映画、マンガなどアート関係の本。この中から読みたい本をリストアップして皆さんと討議する。 落札した本を数冊持ち帰り、その中の1〜2冊を3週間に一度書評するという仕組み。各委員の専門の本だけではなく、趣味系や興味のある系も選んでいいことになっている。 私は、音楽書や美術書はもちろんのこと、ちょっと変わった文芸書や評論書、ミステリー、ジェンダー本やエッチ本までけっこう幅広くとりあげた方だと思う。最初のうちは、何をどう書いても記者さんや読者から反応がなく、自分の書評はそんなによくないのか、と淋しい思いをしたが、そのうちにあちこちから感想をいただくようになり、やりがいもできたし勉強にもなった。 高校から音楽に進んだ私は、系統だった読書というものをしていないし、きちんとした学問大系も持ち合わせていない。それを少しでも補うため、書評する本については、その著者の他の著作やテーマの関連書など、できる限り読んでから書くようにしていた。レベッカ・ブラウンやフィリップ・フォレストなど、翻訳書の刊行に合わせて作家が来日しているときは、講演会やシンポジウムにも出かけて行った。 心残りは、本来書評すべきなのにできなかった本たちである。書く本数に限りがあるのと、基本的に記者さんの選書した中から選ぶことになるので、なかなかうまくいかない。800字で書評したかったのに諸般の事情で400字になってしまった本もある。 書評委員会の役得のひとつは、選書と会議の間にいただくお弁当だ。会席弁当やにぎり寿司、洋食弁当やすき焼き弁当、ウナ重など多彩で、毎回楽しみだった。 作家の川上弘美さんや堀江俊幸さん、高橋源一郎さん、詩人の小池昌代さん、ノンフィクションの与那原恵さん、野村進さん、最相葉月さん、歴史学者の池上俊一さん、武田佐知子さん、文芸評論家の津野海太郎さんや生物学者の新妻昭夫さん、哲学者の鷲田清一さんや経済学者の松原隆一郎さんとお知り合いになれたのは嬉しかったし、委員会を離れても飲み会や旅行など、交流の機会もずいぶんあった。亡くなった種村季弘さんの本に関する蘊蓄を聞かせていただくことができたのも、いい思い出になっている。 関係ないけれど、3年間のお給料の30分の1でダイヤの一文字リング(計1カラット、Dカラー、SI1、エクセレントカット)を購入した。今、薬指でピカピカ光っている。 ネットに最近の書評が掲載されていたので、転載しておく。ついでに、評判のよかった『マリア・カラス』の1200字評(森進一と森昌子は離婚してしまったけれど)。 ●ムーサの贈り物 ドイツ編 [著] 喜多尾道冬 400字 ディスクのジャケットの絵を選ぶのは、弾き手の楽しみのひとつだ。作曲家ゆかりの、あるいは作品とひびきあう図柄を見つけたとき、ようやく仕事を終えたような気がする。 本書は、ジャケットを入り口に、音楽と絵画の幸福な出会いを渉猟している。ブラームスにもとづく連作銅版画集を制作したM・クリンガーは、最後の一葉で作曲家本人から「目に見える音楽」と賞賛された。 作曲家自身が描いた絵がジャケットを飾ることもある。メンデルスゾーンの風景画の柔らかな線と調和のとれた構図は、古典派とロマン派の境目にいたこの作曲家を象徴するようだ。 バロックから現代音楽まで、ジャケットになるのがダントツに多いのはロマン派の画家C・D・フリードリヒの絵だという。楽器や奏者をモティーフにしているわけではないが、静謐(せいひつ)な中に激しいドラマをひそませた画布からは、まぎれもなく音楽が聞こえてくる。 ●永遠の子ども [著] フィリップ・フォレスト 800字 ある日、四歳の愛娘(まなむすめ)がガンを宣告された。大学教授のパパは勤めを切りつめ、医学書を読みあさり、娘と一緒にお絵かきを習い、セーラームーンごっこに興じる。抗ガン剤、脱毛、手術、再発といった過程を記す著者の筆は、対象をつき放せばつき放すほどにじみ出てくる悲しみや喪失感に彩られ、深い感動を呼ぶ。 しかし同時に本書は、一人の作家が生まれる内的過程を綴(つづ)った教養小説として読むこともできる。ソレルスを研究する比較文学者の著者は、「想像したり観察したりできない」自分は創作には不向きだと思っていたが、娘の死を機に書かずにいられない衝動にかられたのである。 死に関する本は沢山(たくさん)出るが、どれもかんじんのところは避けて通っている、と著者は書く。「これみよがしの悲壮感(パトス)なし! だが、そうすると真実は、実際に生きられた不安と悲しみのあの耐え難い結び目は、どうなってしまうのだ?」 とはいえ、書くことの無力は著者を苛(さいな)む。描写しようとしたとたんすりぬけてしまう言葉。どうあがいても忘却を防げないもどかしさ。やはり子どもを失ったマラルメは、息子のために書こうとした本を完成させることができなかった。 試行錯誤の末に著者が選びとったスタンスは、大昔の狩人が洞窟(どうくつ)の壁に残した手形である。「僕はもういない。いただけである」と語るために。「小説は、時間のなかでの勝利――密(ひそ)やかで無意味でささやかな――、栄光のない奇跡である。小さな切り込みが、時間の記憶喪失の厚みのなかに、こっそりと開かれる」 本書を書くとき、著者が下敷きにしたのは日本の私小説だった。というより、彼が私小説の範疇(はんちゅう)に属すると考えていた三島や太宰、漱石の作品。とりわけ、父親の苦悩を真正面から描いた大江健三郎には励まされた。のちに著者は、彼らの大半が、厳密な意味での私小説を批判した人たちであることを知るのだが。 主観性を旨とする日本の私小説は、客観性を旨とする西欧の自然主義への大いなる誤解から生まれたという。とすれば本書は、日本の私小説に対する「美しい取り違え」ら生まれたといえよう。 ●グレン・グールド論 [著] 宮澤淳一 400字 グールド書を多く訳している著者による初の評論。 バッハ「ゴルトベルク変奏曲」の録音の比較が面白い。54年収録の「主情的」なライヴ録音。翌年のデビュー盤の「超越的」演奏。死の前年に再録音された「超・超越的」演奏。 この間グールドは、内的カンタービレを削(そ)ぎ落とし、「触感の慶(よろこ)び」も封印し、独自の方法でテキストを再構築して「演奏のマニエリスム」を完成させた。 著者は、グールドのこうした禁欲主義や客観主義、批評性を、カナダという国の特性に照らして論じる。 アメリカンドリームの対極にあるカナダは、競争原理をすり抜けて超越の方向に向かう。公開演奏を拒否し、録音活動に限定したグールドの身振(みぶ)りも、決して負け犬精神ではなく、優れた発想の転換なのである。 「(北の謎とは)ネガティヴな自然の中でポジティヴな思想を醸造する発想です」というグールドの言葉が、そのことを裏づける。 ●楽器と身体 [著] フライア・ホフマン 800字 一七五〇年から一八五〇年にかけて、オーストリアやドイツの市民階級における女性音楽家の活動とその受け入れ状況を、豊富な資料で検証した本である。 アンネ・ゾフィー・ムター、五島みどり、チョン・キョンファ、庄司紗矢香。世界で活躍する女性ヴァイオリニストの名前はすぐ浮かんでくる。オーケストラでも、多くの女性奏者が活躍している。 でも、当時のドイツ文化圏では、女性がヴァイオリンを弾くことはタブー視されていたそうなのだ。「暴力的で急な動きを要求する」楽器が「女性が守るべき立ち居振舞(ふるま)い」にふさわしくないから。そもそも女性の身体に似せてつくられている弦楽器を女性が弾くのは、同性愛を連想させるということもあったらしい。 かわりに奨励されたのがピアノで、十九世紀前半にコンサートに出演した女性器楽奏者のうち、九割はピアノを弾いていた。といっても、女性は職業をもつべきではないとされていたころだから、彼女たちの多くはアマチュアだった。 後半では、さまざまな社会的規範にもめげず、果敢に職業演奏家を目指した女性たちのエピソードが紹介される。 乗馬でも横座りしなければならなかった時代、一八四五年にデビューしたチェリスト、リザ・クリスティアニは、批評家たちの好奇の目にさらされながらドイツ各地を演奏旅行した。カロリーネ・シュライヒャーも、「口の形がゆがむから」と封印されていたクラリネットに打ち込み、四十年のキャリアを築いた。彼女たちの勇気がジャクリーヌ・デュプレやザビーネ・マイヤーを生んだのだ。 私が思いをはせるのは、日本のピアノ事情である。音大のピアノ科は女子学生で占められているが、プロになる確率は低い。ソリストはそんなにいらないし、ピアノはオーケストラにはないからだ。 息子が音大に行くことは反対する親も娘には許す。就職できなくても結婚すればよい、結婚できなくても家でピアノを教えればよいと考えるからだろう(少子化で、この道も危うくなりつつあるが)。事情は二世紀前のドイツ文化圏とあんまり変わっていないかもしれない。 ●サクリファイス [著] フローランス・デュガ 800字 ポーリーヌ・レアージュ『O嬢の物語』の系譜に連なる哲学的ポルノ。読み手を興奮させる目的で書かれたのではなく(少なくとも、私はあまりきざさなかった)、女性のセクシュアリティについてひとつのケースを提示するというふうな。 帯には「人はこれほど放逸に性愛を極められるのか!」と書かれているが、違うと思う。「世間一般の女たち」のように男を愛そうとしてうまくいかなかった女子大生フローランスは、自分にフィットする愛を求めてあらゆる倒錯的な行為に及ぶが、いつも満たされないままだ。 フローランスをめぐる人物は、大学教師の男性JPと教え子の女性ナタリー。著者は自在な性の置き換えを試みる。ナタリーはフローランスに対してもJPに対しても女性としてふるまうが、フローランスは状況に応じて男にも女にも変容する。ただし、男たちに対してはいつも受け身の立場で、ここがポイント。 JPは二人の女性を加虐趣味で苛(さいな)む。彼女たちがそれを望んでいると察したからだ。二人だけで関係を持つようになったフローランスとナタリーは、互いにSとMの役割を交替(こうたい)させる。そのあまりの過激さに、JPは傍観者の立場に退く。 まさに血みどろのシーンがつづくわけだが、女性の性愛がしばしば苦痛と結びつくというようなSM文学の構図にとどまらず、幼時の回想がフラッシュバックのように挿入されて、そもそもの背景となるゆがんだ親子関係が示唆される。 フローランスはナタリーに自分の反映を見ているのだ。彼女を痛めつけながら、彼女によって痛めつけられながら、自分の中の女性性を破壊しようとしているのだ。父親によって汚された女性性を。 皮肉なことに、唯一フローランスを癒やすことができたのは、彼女に性衝動を感じないゲイの男性ルイだった。暴漢に襲われたフローランスを救った彼は、彼女が本質的に性倒錯者ではないことを見抜き、こう囁(ささや)く。「あなたが女であることをあなたに禁じたのは何ですか?」 この小説で描かれている愛のかたちはきわめてアブノーマルだが、全体は普遍的な命題で貫かれている。 ●吉田秀和全集23―音楽の時間、24―ディスク再説 [著] 吉田秀和 1200字 一九七五年から刊行されてきた全集もついに完結。23巻はレコード誌の連載と朝日新聞「音楽展望」が中心。24巻は未収録のエッセイなど。 休載中の「音楽展望」が始まったのは七一年のことである。「展望」だったから続いたと吉田は書く。これが時評だったら、時のうつろいとともに消え去ってしまっただろう。 実演やディスクを聴きながら、吉田はその芸術家の過去や未来を見ようとする。トルコの新進ピアニスト、ファジル・サイのような溌剌(はつらつ)たる才能を聴くと、先はどうなるかと想像する。カルロス・クライバーの訃報(ふほう)に接すると、優秀な指揮者だったのにどうして仕事を減らしてしまったんだろうと思いをめぐらせる。 吉田は、時代の好みの変遷も見据える。主観主義から客観主義への切りかえ、そして現在の多様なスタイル。彼も含めた評論家たちが六〇〜七〇年代に聞きほれた演奏が、今はつまらなく感じられたり、興味を持てなかった作品に心打たれたりすることがある。いったいなぜか? 耳とそれに直結する心や頭はどんな具合にできているのか。読み手に問いかけ、ともに考える。 吉田の「展望」は音楽にとどまらない。プルースト『失われた時を求めて』の一節、ある貴婦人の「嬰(えい)ト音のように無限に引きのばされていた微笑」を読むと、ワーグナー『トリスタンとイゾルデ』の宿命の嬰ト音を連想してしまう。プルーストは、話者と貴婦人の間に何のドラマも起きないことを皮肉るために、あえてこの音を使ったのではないか、などと深読みする。 文章の喚起力、比喩(ひゆ)のうまさにはうならされる。モーツァルトを弾くブレンデルは、「巨人がわざわざ小さな自転車に乗って苦労して走っている」ようだ。グルダはモーツァルトを弾いたあと、ニヤッと薄笑いを浮かべる。「ひとをバカにしている」ようでもあり、「照れた揚げ句、自分で道化を演じている」ようでもあり。 朝比奈隆にしても、ほんのひとはけで芸術家としてのありようをデッサンしてみせる。 「彼は全身全霊を込めてやりたい音楽を見いだし、いくらやってもこれで終(おわ)りということにならないので、くり返しやらずにいられないということを身をもって示し、それで生き、それで死んだ芸術家だったのである」 いっぽうで、「あんなにぴんぴんしていて、あんなにすばらしい演奏をするのに、何かというとキャンセルする」アルゲリッチにも思いをはせる。吉田もまた、演奏家を襲う継続への疲弊感、ステージに臨むときのような精神的葛藤(かっとう)に苦しめられているのかもしれない。というのは、音楽評論も瞬間の芸術だからだ。疾走する音楽をとらえ、的確な言葉に変換する作業は並大抵ではないし、誰にもできることではない。 読みながら、吉田に評されてきた「音」たちの幸せを思っていた。 ●若かった日々 [著] レベッカ・ブラウン 800字 独特の皮膚感覚に訴えかける文章が魅力のレベッカ・ブラウン。邦訳四作目は相いれない父と母への親和性に引き裂かれた女性をめぐる連作短編集である。 「私」の外見は、父親そっくりだ。青い目、ウェーブのかかった髪、ごつごつした膝(ひざ)。でも、夜中に悪夢でうなされてとび起きる癖は母方の遺伝である。母はそのたびにしっかり抱きしめてくれた。 やがて両親は離婚し、「私」は母親に育てられる。海軍軍人なのに戦争経験がなく、にもかかわらず見てきたように戦場を語る父を、娘は許せないと思っている。男の子がダメな父親を嫌うように。 しかし、彼女自身もホラ話が得意なのである。中学のとき、ほとんどすべての女生徒の憧(あこが)れだったチアリーダーのテストを受けなかった話を、真実を伏せてフェミニズム的英雄譚(たん)に仕立てたりする。 第四話「魚」が見事。父親と海釣りに行った十四歳の「私」は、父の手引きで一匹釣り上げたものの、熱狂する父に、「これ、戻していい?」ときく。戻される瞬間、宙ぶらりんになった二人の気持ちを象徴するように、魚は白く輝いた。 そして、幼時の水にまつわる第八話。母が水を嫌うため、水泳は父から教わった。彼の腕に向けて必死で泳ぐ。時計の金属バンドがはさまりそうな毛深い腕。父は、泳ぎきった娘の肩に手を乗せる。 こうした背景に囲まれた二編では、核となるレズビアン体験が語られる。チアリーダーのテストを受けなかったことをきっかけに、同じ性癖を持つ教師ミス・ホプキンズと出会ってしまう第六話。 「私」は彼女の手を肩に感じる。手首の外側につけた腕時計。この部分が、第八話のエピソードに重なる。青い目の女教師は、父親のかわりだったのだろうか? 全十三編を覆うのは、豊かな音楽性だ。頭の中で音楽が呪文のように聞こえる感覚から作品が始まる、と語る著者は、作曲家が音符を書きとめるように言葉を書く。第十一話の「私はそれを言葉にしようとする」など、そのまま音楽を聴くよう。海のうねりのように襲い、また鎮まる自殺衝動。一行一行が身体組織に浸透し、おもむろに脳髄に上っていく。 ●パリのヴィルトゥオーゾたち―ショパンとリストの時代 [著] W・フォン・レンツ 800字 ショパン一八一〇年生まれ、リスト一一年生まれ。二人とも細身でイケメン。こんなスター作曲家がそろうなんて、音楽史上でも珍しいのではないかしら? 二人の同時代人で、ロシアの音楽愛好家による回顧録である。一八二八年にパリを訪れた著者のレンツは、なんとリストから直々にピアノを教えてもらったのだ。譜例も紹介されているから、ウェーバーのソナタやショパンのマズルカの紙上レッスンを楽しむこともできる。 リスト邸にはピアノが三台も置いてあったが、指定された楽器を弾いたらまるで音が出ない。リストは、「音階を一つさらうのに十倍の効果が出るよう、鍵盤を非常に重くしてあります」と言った。(負荷をかけて指を鍛えるやり方は時代遅れなので、マネしないように) 一八四二年に再びパリを訪れたレンツは今度はショパンのレッスンを受けている。なかなか人に会いたがらないショパンに渡すようにと、名刺に「通行許可証」と書いてくれたのはリストだった。ちなみに、リストはレッスン代をとらないがショパンは相当高かったらしい。 ショパンが好むピアノは、できるだけ鍵盤を軽くしたプレイエルだ。レンツが「リストに習った」マズルカを弾くと、ショパンはちくりちくりと厭味(いやみ)を言う。 ジョルジュ・サンドにも紹介されたが、彼女はひどく無愛想で、上着のポケットから巨大なハバナ葉巻を出し、ショパンに向かって「火を頂戴(ちょうだい)!」と叫んだ。リストが「可哀想なフレデリック」とつぶやいたわけだ、とレンツは納得する。 レンツの回想には誇張や演出がめだつが、証言そのものは信憑(しんぴょう)性があるという。ベートーヴェンのソナタでは「月光」や「熱情」くらいしか弾かれなかったとか、当時の音楽事情もわかって面白い。 きわめつけは、目の前で聴くショパンの自作自演だ。レンツによれば、「楽譜を読んだ印象と、実際に響く現実の音の世界」には食い違いがあった。「彼の意図やピアノについての認識を考慮しないなら、彼の作品は理解されないままで終わる危険性がある」というコメントは、百六十年後の今もそのままあてはまる。 ●イマジネーション―今、もっとも必要なもの [著] 赤川次郎 400字 この本を読んで、あっそうかと思ったことがある。 暗いニュースがあいつぐのに、世の中どこかおかしいという声は一向に聞こえてこない。そんな話よりオリンピックで金メダルをとった記事を読みたがる、と著者は言う。「おそらく人は、自分の暮(くら)しに不満があり、将来への不安を抱えていると、いやな話など聞きたくないのだ」 若い世代に読者が多い著者は、ことさらに時流を追わず、人間は基本的に変わらないというスタンスをとってきた。しかし、昨今はどうも理解不能なことが起こる。生活の底に不気味なものが潜んでいる。想像力の欠如が原因ではないか。 いじめ問題や対人関係。相手の立場に立ってものを考える習慣が失われつつある。人間が想像力を働かせなくなったらどうなるかは歴史が証明しているのに。 大学での講演をまとめた文章は平易ながら核心をつき、著者の抱く危機感がひしひしと伝わってくる。 ●最後の錬金術師 カリオストロ伯爵 [著] イアン・マカルマン 800字 『山師カリオストロの大冒険』の著者、種村季弘さんがいらしたら、舌なめずりして書評なさったに違いない。一七四三年パレルモに生まれ、九五年にローマで獄死したカリオストロの生涯を、豊富な資料を駆使して描いた痛快な歴史物語。 その名はどこかできいたことがあるだろう。ルパン・シリーズ、宮崎駿のアニメ、そしてモーツァルトの歌劇「魔笛」のザラストロのモデルとして。 ときはフランス革命前夜。「理性と啓蒙(けいもう)の時代」十八世紀は、実は(だからと言うべきか?)「いかさまと迷信の時代」だった。カリオストロも、若い妻を使って色事師カザノヴァに近づき、偽造文書を作成してみせたり、東欧の小公国のお姫さまを降霊術でたぶらかしたり。 生まれ故郷の修道院で伝授された医術の腕だけはホンモノだったらしい。処方箋(せん)を調べたら、彼が使っていた薬はすべて無害か有益なものだったという。 無害では効かないじゃないかって? カリオストロはカリスマ性で補ったのだ。その瞳は「言い表しようもない超自然的な深みをたたえていた」という。 ゆく先々で、貧しく病める人々が彼のまわりに群がった。いっぽうで、フリーメースンの支部を利用して上流社会にはいりこみ、錬金術やカバラで人心をつかむ。ばれそうになると、さっさと逃げ出す。メースン嫌いのエカテリーナ二世はだませなかったが、ポーランドの王様やイギリスの皇太子はいちころだった。 一七八五年に起きた「フランス王妃の首飾り事件」が有名だ。女詐欺師ジャンヌが、マリー=アントワネットの名をかたり、五百四十個ものダイヤでできた首飾りを盗んで逮捕された。彼女は、カリオストロに罪をなすりつけるのだ。 裁判で冤罪は晴らすが、カリオストロは国外追放となる。このとき発表した文書は、収容されていたバスティーユの陥落や革命を予言したとして騒がれた。正確には当たっていないのだが、ただならぬオーラで信じさせてしまったのだ。 波瀾(はらん)万丈の生涯に快哉(かいさい)を叫ぶもよし、こういう人物を跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)させた「時代」をかいま見てため息をつくもよし。 ●コマネチ 若きアスリートへの手紙 [著]ナディア・コマネチ 800字 本書を読みながら、満点を取る精神構造というようなことを考えていた。 76年モントリオール五輪の「白い妖精」コマネチが、若い体操選手からの手紙に答える形で半生をふり返る。段違い平行棒や平均台で史上初の10点満点を七回も出したとき、彼女はまだ十四歳。可憐(かれん)な容姿で一躍ヒロインとなった。 驚嘆すべきは切り替えの速さだ。アテネ五輪のホルキナは、得点のたびに感情をあらわにした。魅力的だったが、肝心なところでミスを重ねた。コマネチは、初めて10点を出したときですら、すぐにそれを忘れた。表彰台に立っている間も、演技の反省点を探して次にそなえる。 コマネチの出現は女子体操を「美」から「技」に変えたが、そこには、コーチのベラ・カロリーが深くかかわっていた。彼は四千人をテストして小柄な少女たちを集め、食事や練習を徹底的に管理した。のちに彼はアメリカに亡命し、やはり金メダルを獲得したが、この名コーチにスポイルされる選手も続出した。 あなたも子供時代を犠牲にしたのかときかれたコマネチは、こう答える。自分はもともと高いところから飛び降りるのが大好きだった。体操は、想像もしない形で宙を舞う機会を与えてくれたのだ。 コマネチは、過剰なトレーニングにつぶされない秘訣(ひけつ)を教えてくれる。自分はいつも予備の力をとっておいた。許せる痛みと無駄な痛みを分けて考えた。カロリーには常に叱咤(しった)激励されていたが、故障する危険はなかった。彼は、自分の本当の限界を知らなかったのだから。 ピアノ教育に携わる私には、このコメントの凄(すご)さが身にしみる。周囲の期待、指導者の野望の犠牲になる例は数多くみられるが、大成するかどうかは、本人が自分の能力をどこまで掛け値なしにみきわめられるか、にかかっているのだ。 チャウシェスク元大統領の次男との関係など、暴露話を期待する人は肩すかしをくうかもしれないが、演技と同じように贅肉(ぜいにく)をそぎ落としたコマネチの「言葉」は、そんなゴシップ的興味を一掃する。スポーツのみならず、広く教育全般にかかわる人に読んでほしい本だ。 ●「マリア・カラス」 [著] ユルゲン・ケスティング(鳴海史生訳) 1200字 もし森進一が、奥さんの森昌子のような澄んだ声で歌えといわれたら。もし美空ひばりが、ドスのきいた低音部、鼻にかかる中音部、きれいなファルセットと三種類の声を持っていることを非難されたら??。 ね、ありえないでしょ。ギリシャの生んだ不世出のオペラ歌手マリア・カラスは、まさにその点で批判されたのだ。ライヴァルだったテバルディのように天使のような声ではない、あるいは声域がなめらかに移行しない、等々。 映画「永遠のマリア・カラス」を観(み)た人なら知っているだろう。生誕八十年を迎えたカラスの生涯は、数々のドラマティックな伝説で彩られている。ダイエットで百キロ近い体重を六十キロ台に落としたこと。かのジャッキー・ケネディと海運王オナシスをとりあったこと。 でも、そうした逸話だけで語るには、カラスはあまりに革命的な存在だった。個性的な声、優れた演技力と役柄に対する深い洞察。大衆音楽や演劇なら是非(ぜひ)とも求められる資質が、当時のオペラ界では必ずしもプラスに作用しなかったことに驚かされる。音楽はひとつ、舞台芸術もひとつなのに、どうしてジャンルが異なるとこうも価値観が変わるのか。どうして、そのことで不当に苦しむアーティストがいるのか。 本書はそんな問題点をズバリとついてくれる珍しい研究書である。画期的なのは、彼女の歌唱を「黒いロマン主義」と呼び、十九世紀的な負の美学の中に位置づけたことだろう。 「マリア・カラスは、『苦悩』の声、『残忍さ』の声、『夜』の声、何か『奥深いもの』のための声、ということはすなわち、『魂の状態』の表現にふさわしい声をもっていた」 とりわけ、彼女がスカラ座で復活させたヴェルディ「マクベス」のマクベス夫人や、ケルビーニ「メディア」のタイトル・ロールは、「天使のような声」では実現不可能な役柄だった。 カラスの歌手人生は異様に短かった。声に問題をかかえずに歌えたのは十二、三年。最盛期は五一/五二年から五四/五五年のシーズン。「マリア・カラスは、両端から燃える蝋燭(ろうそく)のごとく、見る見るうちに消滅してしまった」と著者は語る。それは何故(なぜ)か??。急速に進む商業主義の犠牲になったともいえる。しかし、原因の大半はカラス自身が招いたものなのだ。 「彼女は自分の声をいたわらず、手入れせず、管理せず」、若いころから「歌手殺し」と呼ばれる役を歌いすぎた。オペラ歌手の曲芸的な側面、「アイーダ」二幕フィナーレの高い変ホ音など「力技」の呪縛からも抜けきれなかった。とはいえ、「彼女の偉大さは、成功の幸福のみならず、失敗の仕方にもある」。 伝説は極力排除し、録音を徹底的に聴きこむアプローチから、芸術家としてのカラスの壮絶な戦いが3D画面のように迫ってくる。
|
| MELDE日記・目次 |
| ・2009年7月23日/受賞とテレビ出演 『青柳いづみこの MERDE! 日記』で一部削除 |
| ・2009年1月8日/パリ近郊のコンサート |
| ・2008年10月16日/人生みたいだったドビュッシー・シリーズ |
| ・2008年7月27日/天使のピアノのレコーディング |
| ・2008年7月23日/5月のメルド! |
| ・2008年3月23日/母の死とドビュッシー・シリーズ |
| ・2008年1月5日/ドビュッシー・イヤーの幕明け |
| ・2007年11月5日/大田黒元雄のピアノ |
| ・2007年9月20日/ビーイングの仕事 |
| ・2007年8月19日/越境するということ |
| ・2007年4月9日/吉田秀和さんの文化勲章を祝う会 |
| ・2007年2月9日/カザフスタンのコンクール ( II ) 『ピアニストは指先で考える』に収録 |
| ・2007年1月20日/カザフスタンのコンクール ( I ) 同上 |
| ・2006年9月12日/10冊めの著作が出版されます! |
| ・2006年6月20日/美術とのコラボレーション |
| ・2006年1月5日/750ユーロの時計 |
| ・2005年10月25日〜11月2日/セザンヌの足跡を追って──南仏旅行記 |
| ・2005年9月30日/『ぴあ・ぴあ』ただいま7刷中 |
| ・2005年8月28日/”気”の出るCD? |
| ・2005年7月6日/ラジオ深夜便 |
| ・2005年6月23日/ぴあ・ぴあ (*) 『青柳いづみこの MERDE! 日記』で一部削除 |
| ・2005年5月30日/第7回別府アルゲリッチ音楽祭 『青柳いづみこの MERDE! 日記』で一部削除 |
| ・2005年4月10日/朝日新聞の書評委員 |
| ・2005年3月27日/ジャス・クラブ初体験 |
| ・2005年3月20日/パリでメルド! トーキョウでメルド! 2) |
| ・2005年2月26日/パリでメルド! トーキョウでメルド! 1) |
| ・2005年1月5日/吉田秀和さんの留守電 |
| ・2004年12月20日/音楽は疲労回復に役立つ! |
| ・2004年11月22日/有名にならない権利:クートラスとアルカン |
| ・2004年10月23日/14年越しのエッセイ集 |
| ・2004年10月5日/プレイエルとベヒシュタイン |
| ・2004年8月25日/アテネ五輪 アナウンサーと解説者のビミョーな関係 |
| ・2004年年7月4日/松田聖子体験 |
| ・2004年6月1日/「メロン三姉妹」と美智子さま |
| ・2004年4月16日/アンリ・バルダ追っかけ記 『アンリ・バルダ 神秘のピアニスト』に収録 |
| ・2004年3月10日/小さな大聴衆 |
| ・2004年1月20日/大変なんです!! |
| ・2003年12月12日/テレビに出てみました |
| ・2003年9月13日・14日・15日・16日・17日/方向音痴のシチリア旅行 その II |
| ・2003年9月10日・11日・12日/方向音痴のシチリア旅行 その I |
| ・2003年9月8日/アンリ・バルダの講習会 『アンリ・バルダ 神秘のピアニスト』に収録 |
| ・2003年8月17日/東京湾大花火大会 |
| ・2003年7月28日/世界水泳2003バルセロナ |
| ・2003年7月11日/新阿佐ヶ谷会・奥多摩編 |
| ・2003年5月31日/アルゲリッチ−沖縄−ラローチャ[III] |
| ・2003年5月28日/アルゲリッチ−沖縄−ラローチャ[II] |
| ・2003年5月22日/アルゲリッチ−沖縄−ラローチャ[I] |
| ・2003年5月3日/無駄に明るい五月晴れ |
| ・2003年4月5日/スタンウェイかベーゼンか、それが問題だ。 |
| ・2003年2月12日/指輪 『青柳いづみこの MERDE! 日記』で一部削除 |
| ・2003年1月13日/肩書き |
| ・2002年12月23日/年の瀬のてんてこまい |
| ・2002年12月9日/批評とメモ |
| ・2002年11月6日/アンリ・バルダのリサイタル 『アンリ・バルダ 神秘のピアニスト』に収録 |
| ・2002年10月21日/なかなか根づかないクラシック音楽 |
| ・2002年9月26日/青山のブティック初体験 |
| ・2002年9月3日/鹿鳴館時代のピアノ |
| ・2002年7月19日/竹島悠紀子さんのこと。 |
| ・2002年6月13日/ 生・赤川次郎を見た! |
| ・2002年5月6日/海辺の宿 |
| ・2002年3月28日/新人演奏会 |
| ・2002年3月1日/イタリア旅行 |
| ・2002年2月5日/25人のファム・ファタルたち |
| ・2002年1月8日/新・阿佐ヶ谷会 |
| ・2001年11月18日/ステージ衣装 |
| ・2001年10月26日/女の水、男の水 |
| ・2001年9月18日/新著を手にして |
| ・2001年8月/ホームページ立ち上げに向けて |
Copyright(c) 2001-2005 WAKE UP CALL |